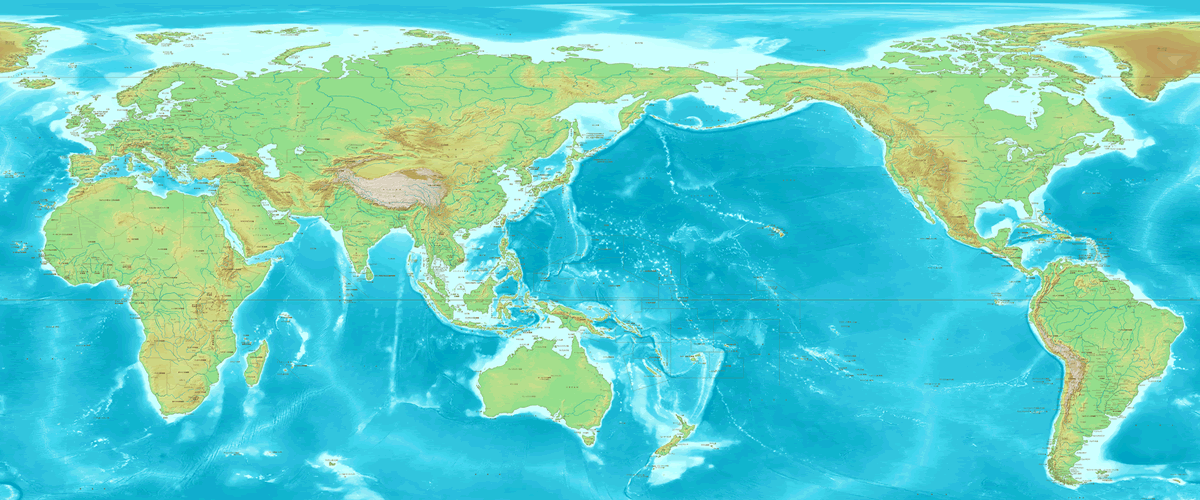Monsanto, Portugal

Monsanto, Portugal
19~21.03.2013
「ポルトガルで最もポルトガルらしい村」と謳われる、モンサントへ。
リスボンのバス・ターミナルからブラガ行きに乗り3時間。
カステロ・ブランコでモンサント行きにバスを乗り換え2時間弱。
ヨーロッパでの移動時間は、南米でのそれに比べてとても短い。
少し考え事をしていると、すぐに目的地に着いてしまう。
アルゼンチンでの68時間乗りっぱなしのバス移動と、
ベネズエラからコロンビアへの0泊5日のバス移動が、
僕の感覚を著しく狂わせたのだと思う。
リスボン14時発のバスに乗り、モンサントに到着したのは19時過ぎ。
辺りはもう暗くなり始めていた。
とてつもなく静かだ。人っ子ひとり歩いていない。
そして、寒い。空気が、ピインと張りつめている。
そしてこの景色。
僕は思い切り深く深呼吸して、宿を探しに歩き始める。
石畳に転がすスーツケースの音が街に響く。
2001年版「地球の歩き方」には宿は一軒しかないと書かれていたが、
歩いてみると宿を表すのであろう「AL」と書かれた看板が多くはないが、ある。
しかし、今はシーズンではないのだろうか、どこも人の気配がない。
人の気配の有無を感じるほどの静けさ。
完全に日が暮れた街を歩き、いくつかの宿をノックをしてまわっていると、ひとりのお婆さんが出てきてくれた。
なるべく安い宿を探している旨伝える。
「こんな時間に宿探しとは酔狂なこったね、お兄さん。うちは45ユーロだけど、お兄さんお金ないんだろう、そういう顔してるよ、わかるんだよわたしゃ。そうだね、40ユーロにまけとくよ、どうだい。」
と言っていたか定かではないが、おおまかにはそんなことを言われたように思う。
しかし、1泊40ユーロでは長期旅行者の僕には高すぎる。
見させてもらった部屋も、とても良さそうだったし、お婆さんの雰囲気も好みだったが、心を鬼にして僕は聞く。
「マイズ・バラート・ホスタル、ナォン・テン?」
(もっと安い宿はない?)
「あたしゃ知らないよ、他を当たりな。」
「シー、オーケ。ムイト・オブリガード。」
(そっか、わかった。どうもありがとう(握手を求める))
「なんだい兄さん、冷たい手をしてるね。…しかたない、宿はタダでいいよ、泊まって行きな。」
…なんて言ってもらえるわけもなく、次のホステルを探す。
そして見つけた宿は、残念ながら満室。しかし、英語が伝わる。
とにかく安いところを探している旨伝えると、この街で最も安いホテルを紹介してくれるとのこと。
「ポルトガルで最もポルトガルらしい村の最も安いらしいホテル」に泊まれることになった。
どこかに電話して、何やら交渉してくれているようだ。
街の地図に現在地と僕が行くべき宿の場所をポイントしてくれ、地図もいただく。ありがたい。
僕は意気揚々と、盛大なガタゴト音を響かせながら石畳の坂を下り、ほどなく、やっぱりひと気のないホテルに到着。
しかし、ここで待てと言われたからには待つしかなく。
街を眺めながら、5分ほど待っただろうか。
静けさの街に小さな足音が聞こえ始める。白髪にあたたかそうなフードをかぶったお婆さんが現れた。
「あんたかい、こんな何もない街にわざわざやってきた派手な格好の日本人ってのは。噂になってるよ。おや、日本人の割にはずいぶん大きいじゃないか。なにかやってたのかい。」
「はい、バスケット・ボールをやっていました。ポジションは流川と同じでした。」
「流川?誰だいそれは。まあいい、うちは1泊30ユーロだ。2泊で50ユーロだよ。どうするかね。」
「Wi-Fiはありますか?」
「ワイン?そこらじゅうにあるよ。水より安いんだからいくらでも飲めばいい。」
「わかりました。朝食はつきますか?」
「寒いだろう、この街は。でも雲行きを見るに、明日は晴れるよ。昼はあたたかくなる。それまで辛抱しな。朝食はつかないよ。」
「わかりました。ありがとうございます。」
以上のやり取りは全て僕の脳内で行われたものだ。
老婆の口調がラピュタのドーラに近くなってしまうのは、
この街がパズーが働くあの鉱山街の夜の雰囲気に似ていたからかもしれない。
ともあれ、2泊50ユーロWi-Fiなし朝食なしシングルに泊まれることになった。
宿には僕以外誰もいないようだ。
白い息を吐きながら、テラスに出る。
耳が痛くなるほどの静寂。
ずっと遠くで鳴いている犬の鳴き声。
風向きでときおり聞こえるどこかの家のかすかな話し声。
久しぶりに聞いた、煙草が燃えるジジジという音。
ふと懐かしさが僕を包む。
ああ、これは故郷だ。
雪国、岐阜県飛騨市神岡町の冬。
深夜、降り積もった雪の中をひとり大津神社まで歩き、境内に腰をおろし吸った煙草。
もう忘れていた遠い過去の音。
あれを聴いた気がしたのだった。
20時を告げる時計台の鐘が鳴る。
我に返る。
そう、ここは故郷ではない。
あの小さな街から何万キロも離れた場所。
僕は、ここに来てよかった。
いつもより深く眠った朝。
テラスに出ると、青い空が広がっていた。
僕はギターを背負い、街の入り口のカフェへ。
昨夜は閉まっていたが、ありがたい、開いていた。
ハムとチーズの焼いたサンドイッチを食べ、コーヒーを飲む。
準備は整った。
アイム・レディ・トゥ・ゴー。
僕は新しい空気を纏い、
モンサントの街を歩き始めた。